 |
|||
| 令和6年12月8日 講師:石本静子さん |
|||
| 栃は水窪の食文化に欠かせない食材です しかし近年 栃の実を拾い皮をむき さわして栃餅を搗く家庭はめっきり減り 2軒の製菓店の「栃餅」だけが水窪の お土産として残っているのが現状であり 大切な水窪の文化の宝が消えていこうと していることに危機感をいだきます。 皆で勉強して水窪の栃の食文化を次世代に 残していきたいものです。 |
|||
| ◎栃の皮むき | |||
| 完全に干した栃を容器に入れ熱湯をかけ 一晩置く 手が入るくらいのお湯の中で温めながら 一粒づつ皮をむいていく |
|||
 |
|||
 |
|||
 |
|||
| 栃の実を回しながら数回押して実と皮をはがす 柔らかくなった皮を指の腹で剥いていく (爪を使うと爪の間に入って痛いから) 包丁を使っても良い |
|||
 |
|||
| ◎栃のさわし方 | |||
| ・皮をむいた栃を晒の袋に入れ 流れる水に1週間から10日さわす。 実をなめてみて苦みを感じる程度で良い。 ・各家で沢にさわし場という場所を持っていた |
|||
| ・1升の栃の実に十能山盛り1杯の灰をかけ、 良くまぶす。 (灰は杉桧ではなく広葉樹。そばがらもだめ) |
|||
| ・上から熱湯を少しづつ回しかけ、栃の実が ひたひたになるくらいにする。 |
|||
| ・粗熱が取れたら器ごと大きなビニール袋に入れ 口を閉めて1週間くらい置く |
|||
| ・栃の実を取り出し、きれいに洗って 灰をとり3日くらい水に浸けておく |
|||
| ◎栃餅のつき方 | |||
| ・水から上げた栃の実をもち米の上に 乗せて、一緒に蒸す ※実を粉にしても良い 実だけを別に蒸しても良い |
|||
| ・もち米と一緒につく | |||
| ・栃餅は塩をつけると苦みが増す ・くるみタレ、小豆餡、きな粉、砂糖、醤油、塩 などで食べて見て 美味しい食べ方を探る |
|||
 |
|||
| ◎栃粥の作り方 | |||
| ・米、こきび、大豆、ひえ、粟などと 土鍋で ゆっくり炊く |
|||
 |
|||
 |
|||
| 栃をすり鉢でする | |||
 |
|||
| あわ、ひえ、こきび、こめ等の粥の中へ 栃を入れる 入れた物が混ざるように一度沸騰させて から弱火にする 土鍋の下へ古いフライパンを敷くと 粥が焦げ付かない |
|||
 |
|||
| 水窪は田んぼがないので栃の実は大切な 食料であった 栃山という栃の木を植えた山を持っていて 大切にしていた マロニエの実は食べられない 競馬馬がねん挫した時栃を皮ごとつぶして 小麦粉と酢を混ぜ患部に貼ったという話を 聞いた |
|||
| 石本さんが60年前植えた栃の木に ようやく塔が立った(花が咲いた) でも栃の実の数は少なく 実用には 更に年月を必要とすると話された |
|||
| 水窪の栃の木は近年テーブルなどに 使うため伐採販売されて少なくなった |
|||
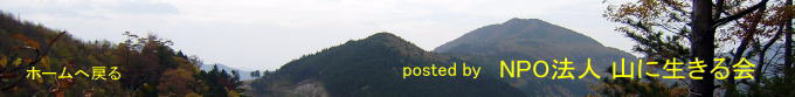 |
|||